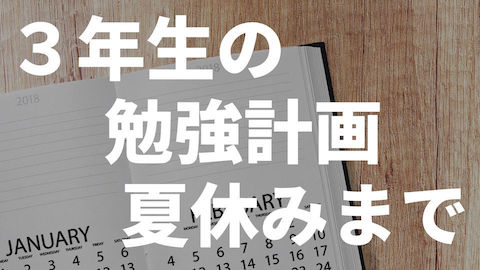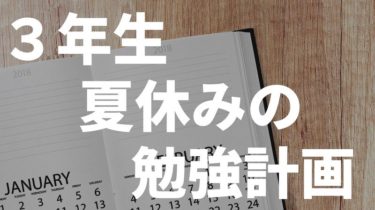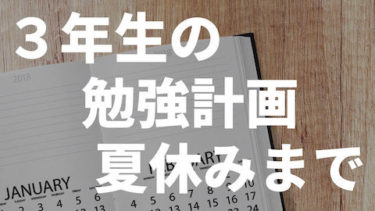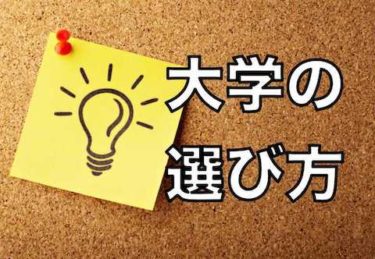この記事ではこんな疑問を解決します。
- 3年生の一学期にどんな勉強をすればいいの?
- 3年生の一学期の何をやるべきか具体的に教えて欲しい
このブログでは主に国公立を目指す理系の生徒を対象にしています。もちろんそれ以外の生徒の皆さんにも十分応用してもらえるように書くつもりをしています。
全員が初心者の受験生
高校3年生は全員例外なく、初めての大学受験です。経験を生かしてというのは無理な話。でも無計画で突き進んでいくのはコワ過ぎる。そんな理系高校3年生の人たちに大学受験に成功する受験までにやるべきことを具体的にお教えします。これは、私自身も実行し、多くの受験生にも教えたものです。是非参考にしてみてください。
受験生がやるべきこと
時期別に受験生がやるべきことをまとめて行きたいと思います。これを参考に是非自分でカスタマイズして1年の計画を立ててみてください。
〜3月(3年生になるまで)
勉強の習慣をつける。土日を大切にしよう。
2年生の終わりには、3年生に備えて学習の習慣をつけておきたいですね。特に土日休日です。
部活をやっていて物理的に平日勉強時間をなかなか取れない人も多いかと思います。時間のある土日にやるかやらないかで大きな差が生まれます。土日の半日はしっかり学習に当てましょう。
細切れではなく、まとまった時間(3〜4時間)学習する習慣は今後の受験勉強に必要不可欠なものです。
1月には入試1年前になりますね。少なくともそこからは受験を意識したいものです。1月〜3月の3ヶ月間休日はおよそ30日間あります。
30(D)×4(H/D)=120(H)
120時間の差ができますね。120時間あれば、3年生になるまでに多くのことが復習できます。この差を後から埋めるのは大変ですよね。早くにスタートを切りましょう!
ここで取り組む内容は、次で取り上げる4月〜5月の内容を前倒ししてやるのがベストですが、現在授業で習っている箇所の予習・復習をしっかりやるということだけでも十分です。
今やっているところは、後々復習しなくても問題演習に入れるようにしておくだけで後からかなり余裕ができます。
日頃から口うるさく言われていることだと思いますが、実際にできている人はどれだけいるでしょうか?まずそれからやりましょう。それで120時間のアドバンテージが生まれるわけです。
4月からの計画を立てる
同時にやっておきたいのは、4月以降の計画(何をやるか)を立てることです。
具体的には次に見ていきますが、理系のみなさんは、ある程度得意な理系の科目を中心に据えるのが良いでしょう。余裕のある人は前倒ししてやりましょう。
4月〜5月(最初の模試まで)
6月の模試を目標に計画を立てよう
いよいよ3年生になりました。ここで、目標にしてほしいのが3年生最初の模試です。
ほとんどの学校は6月頃に設定されていると思います。学校により違うかもしれませんが、マーク模試が設定されていることが多いです。
そのマーク模試を目標に計画を立て、実行しましょう。その理由は
⚫︎マーク模試は基本問題のため、2ヶ月で十分に得点伸びる
⚫︎マーク模試は少し形式に慣れておくだけで、得点が伸びる
⚫︎2ヶ月という期間は計画が立てやすい
などが挙げられます。
苦手ではない理系科目から手をつけよう
苦手ではない理系の科目から手をつけましょう。
苦手科目は2ヶ月では結果が出にくいため、苦手ではない科目からやりましょう。特に得意・不得意がないという人は、数学・化学から始めるのがオススメです。
数学は公式を復習し、教科書の「問」レベルの問題が解ければ、偏差値60が出ます。
化学は覚えるだけでも得点が拾え、単元で独立しているため、2ヶ月で区切りがつけやすいからです。
物理は、この時期は難しいと感じている人が多く、もう少しじっくり時間が取れるようになってから(部活を引退するなど)しっかりと向き合った方が良いでしょう。もちろんある程度得意な人は、こちらから始めても良いと思います。
それぞれ以下に何をすべきか書いておきますので参考にしてください。
⚫︎参考書(チャート等)の難易度2までの例題(練習問題はしない)
もしくは
⚫︎授業で使った問題集の※がついている問題。
オススメはチャートなどの参考書を使うことです。その理由は例題ですぐに解答が確認できるからです。答えの冊子と問題の冊子を行ったり来たりするのは面倒で効率が悪いからです。もちろんまずは問題だけをみて、考えてから解答を見るようにしてください。ただし、2分考えて分からなければ解答を確認してください。
このレベルの問題は考える問題ではなく知っておく問題です。考えて自分でやり方を導き出す必要はありません。やり方を仕入れましょう。解答をみてやり方がわかったら、もう一度1から自分で解いてください。最初から最後まで自分で解けるようになるまで同じ作業を続けます。これをやらないといつまでも身につきません。
難易度1の問題などで明らかにできる問題は飛ばしましょう。
⚫︎教科書傍用問題集(定期テストで使っている問題集)の基本問題・練習問題をやり直す。応用問題はやらない。
これだけで十分です。化学に関しては忘れているところは教科書を必ず読みましょう。化学では教科書は他のどの参考書よりも重要です。必ず教科書を用意して学習しましょう。
数学も化学もこれだけをしっかりやれば、偏差値60は必ず超えます。
「こんな基本だけでいいの?」と思うかもしれませんが、これだけをやり遂げるのもなかなか大変です。世の中の高校生は勉強しません。これだけやれば大きな差をつけられます。
センター(共通)試験の模試を自分でやろう
本番の模試までに、自分で模試をやってみてください。
問題は各予備校が出している昨年のセンター対策用模試を先輩などからもらって手に入れておくのがベストですが、それが難しければ、センターの過去問でも構いません。
その場合は去年のものではなく、ある程度古いものにしましょう。理由は年度が近いものは、受験が近づいて力がついてからの力試しに取っておいた方が良いからです。
今は、何点取れるかより、どういう形式で出題されるのかに慣れておくためにやります。
そのために、4月の最初に一度やります。大問1には何が出て、大問2には何が出てということをチェックします。そして、点をとるためにどこから勉強を始めるか計画を立てます。勉強すれば点が取れるようになりそうな単元から学習を始めましょう。
2回目は6月模試の少し前に、やったところがちゃんと得点できるか確かめるために行いましょう。そこで微調整します。理系科目+英語は2回やっておきましょう。
この模試の模試を自分でやるということは必ずやった方が良いです。それだけで点数は上がります。点数があがればモチベーションアップに繋がりますね!
もちろん、4月までに取り組んでいた、現在の授業の予習・復習は継続させましょう。
6月〜7月(夏休みまで)
ほとんどの人は部活も引退し、本格的に勉強時間を確保できる時期です。ここまでに、学習習慣を身につき、やるべきことをきっちり計画できているとそうでない人はスタートダッシュにかなり差がつきます。
さて、具体的に何をするかみて行きましょう。
数学・化学
上記の内容をしっかりやった人は、マーク模試でそこそこの結果が出たと思います。
その人たちは、数学・化学はそのまま継続して全範囲やって行きましょう。この2ヶ月でここまでの全範囲終えるのが目標です。そこから逆算して計画しましょう。
やることは基礎基本です。夏までとにかく基礎基本。
物理
時間ができるこの時期から物理を本格的に始めます。やる内容は化学と同じです。
化学と同じく、教科書を読みながらやります。特に定義が曖昧な人は要チェックです。
これができる人はそれで良いのですが、とにかく物理がちんぷんかんぷんだという人は、1冊参考書を買いましょう。
オススメは『橋元流解法の大原則(力学・波動) 』です。同じ著者の『橋元の物理をはじめからていねいに【改訂版】力学編 』でもいいかもしれません。
実際、立ち読みしてみて読みやすそうな方にしましょう。本当に一番基本的な考え方を解説してくれている良書です。
とにかく、夏休みまでに力学の基礎基本だけはできるように頑張りましょう。できれば、波にも入りたいところです。
英語
英語は、スキマ時間でできることが多いです。主に単語・構文です。文章和訳に関しては、学校授業の予復習をきっちりやって授業を受ければ力はついていくと思います。
他の理系科目は問題演習中心でまとまった時間がどうしても必要です。英語はスキマ時間を活用しましょう。
ただし、スキマ時間も計画してください。「ちょっと時間ができたからやる」のではなく毎日ルーティーンにしてください。
例えば、
- 通学の電車・バスの中
- 1時間目が始まる前の20分
- お風呂に入ってから寝るまでの20分
などです。毎日決まったスキマ時間を作りましょう。
模試の結果を考察して夏休みにやらなければならないことを計画しよう
模試の結果を踏まえて、これまでの学習を振り返り、各教科夏休みにやらなければいけないことを考えてください。
基礎基本を継続してやっていく科目、少しずつ標準問題へと入っていく科目など、各自の持っている力によって変えていく必要があります。
無計画で夏休みに突入することだけはやめましょう。
合否を分ける夏休みへ
夏休みをいかに過ごすかによって合否が決まると言っても過言ではありません。ここまでは「夏休みのための準備」だったのです。
少し長くなりましたので、夏休みは別の記事で紹介します。是非ご覧ください。
夏休みの勉強方法はこちら
この記事ではこんな疑問を解決します。受験生の夏休みはどんな勉強をすべきなの?受験生の夏休みに各教科、何をどれだけやるべきか具体的に教えて欲しいこのブログでは主に国公立を目指す理系の生徒を対象にしています。もちろんそれ以外の生[…]
今回紹介した参考書など
物理が全然分からないという人にオススメ
イメージでわかる物理基礎&物理 橋元流解法の大原則(力学・波動) (大学受験BOOKS)
問題演習の参考書や問題は基本的にすべて学校で買っているもので良いです。新しく買う必要はありません。